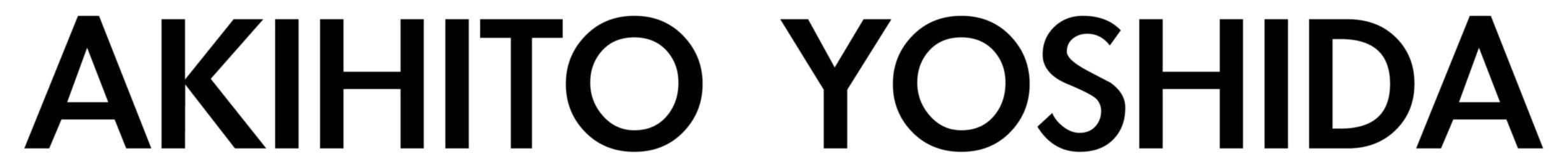大草原のまっただ中にいた。
まるで砂丘のような草原の丘がいくつも続いていて、僕がこれまで見たこともなかった光景が続いている。空を見上げると空気が薄いせいか、それとも空に近いせいか、深く濃い碧がどこまでも広がっている。
その碧の中を巨大な翼を広げたハゲワシが旋回している。百羽以上はいるだろうか。
ゆっくりと旋回をしていたかと思うと、シューンというするどい音を立てて急降下してくるハゲワシ達。中には僕の頭上スレスレを飛んでいく輩もいたりするので、首根っこをつかまれて連れ去られるんじゃないだろうかと少し不安になりながら草原を進んだ。
この大草原へ何をしに来たかというと、「鳥葬」を見るためだ。
鳥葬とは猛禽類の鳥達に遺体をついばませ処理してもらい天へと還す葬儀のことだ。
チベットではこの鳥葬が一般的に行われている。
どの町にも大抵鳥葬を行う場所である「鳥葬台」があり、人々は当たり前の様にそこで自然へと還って行くのである。
彼らチベット人の考え方によれば、天へと還って行った魂はまた新しい命となってこの世に戻ってくるという輪廻転生の考え方が根底にある。
彼らにとっては「魂」こそが「生」へと通じており、その魂の離れた肉体はただの抜け殻に過ぎないのである。
その“抜け殻”を他の生き物の糧にしてもらうことで、今まで人間が生きるために奪ってきた様々な命に対してせめてもの恩返しにもなるのだろう。
鳥葬にはそのような仏教的な考えが背景にあるのだ。
僕はその鳥葬が行われるというその場所にたどり着いた。
鳥葬が行われる日は不定期なのだが、僕がそこへ行った時は既に遺族達が鳥葬の準備を始めるために集まっていた。
その場所は、四角く切り出された石が置いてあるだけの、何の変哲もない場所だった。
鳥達を眼下に眺めながら、しばらくそこに立ちつくしていると、何やら大勢の男達が、透明の袋を抱えて丘に登ってきた。
その袋を抱えた男達は、透明袋から黄色い布で包まれた小さなそれを出し、ほどき出した。
果たしてその包みをほどくと魂の抜けた人間の肉体が、腐臭と共に僕達の眼の前に現れたのである。
青空と大草原の下に現れたそれは、ダランとだらしなく手と足を投げだし、力なく宙を漂っているかのようだった。
大勢の男達がその魂の抜けた肉体を囲んでいる。
僕はその光景を見ながら、不思議な感覚にとらわれていた。
眼の前にあるその肉体には確かに「魂」は宿っていなかった。
それを大前提として知っていながらも、どこかでその光景を信じることのできない僕の心があったのだ。
僕は眼の前の現実と自分の心とが段々剥離していくのをこの時リアルに感じていた。
それは同時に、「死」に対しての僕のこれまでの認識が覆される瞬間であったのかもしれない。
眼の前にある魂の抜けたその肉体のように、僕自身もフワフワと力なく宙を漂いながら、ただただその光景をじっと見つめた。
その肉体は男性のものだった。
死後何日経過しているのか分からなかったが、肌は土色に変色し、手足は不自然な方向を向いている。
遠目から見てもその肉体が体温を失い、固く冷たくなった様を感じ取ることが出来た。
その死んだ肉体の放つ臭いにつられてか、今までおとなしくしていたハゲワシ達がにわかにざわつき始め、集まってきた。
しかし大勢の男達が死体を囲んでいるため、近づくことはできず、ただただ「その時」が来るのを黙って待っているのがどことなく不気味であった。
大勢の男達が死体を取り囲みじっと見つめるその中で一人死体の側でしきりと動いている男がいた。
その男は、青いビニール袋を被りスッポリと体を覆い、手にはナイフが握られている。
そしてこともあろうか、そのナイフで死体を切り刻んでいるのである。
うつ伏せにされた死体は背中から腕から足、そして頭と次々と切り刻まれ、僕達が普段目にすることのない、薄皮一枚隔てた内側の肉を露にされている真っ最中だった。
しかしこれは何も死者を冒涜した行いではなく、あらかじめ細かく切り刻むことによってハゲワシ達が死体を食べる時に食べやすい様にするための作業なのである。
そんな作業がおよそ10分は過ぎただろうか。
うつ伏せのその死体は完全に切り刻まれた。
そして、ナイフの男が立ち上がり、男達が死体の側から離れた瞬間!!
今までおとなしくしていたハゲワシ達が
「ギャーッ!!!」
と雄叫びを上げながら、一斉に死体に飛びかかった。
「ギャーッ!!グルルルル!!」
凄まじい数のハゲワシが死体に群がり、あっという間に死体は見えなくなる。
鋭いくちばしで肉をついばむごとに、ハゲワシ達の頭が血で真っ赤に染まっていく。
時々、自分の”えさ”を巡ってハゲワシ同士で激しい喧嘩をするものもいる。
自分の”えさ”を横取りされまいと、必死の攻防戦だ。
そして時々勢い余ってついばんだ肉片がポーンと空中に飛び上がり、その騒ぎの中心からこぼれると、その肉片を追いかけて数羽のハゲワシが群がる。
そしてその”一切れ”を巡ってまた激しい攻防戦が繰り広げられるのだった。
僕はその光景を身震いしながら見た。
それは今までに見たことのないこの光景と、自然のあまりの厳しさに触れたからかもしれない。
或いは、チベット人の死生観に多少なりとも触れることのできた喜びからかもしれない。
様々な想いが僕の体中を駆け巡り、全身をもって何かを感じようとしているのが分かった。
そんなことを他所にハゲワシ達は生きるための戦いを展開していた。
何分ぐらい経っただろうか。
先程のナイフの男が棒切れを持ってやってきて、ハゲワシ達を叩きながら追い払い始めた。
そして死体からハゲワシが去った後、そこにあったのは、「骨」だった。
確かにさっきまであった柔らかな肉は、ハゲワシの胃袋にきれいに収められたという当たり前の事実をその骨は語っていた。
ナイフの男は、骨だけになったその死体に近づくと、ナイフを斧に持ち替え、骨という骨を砕き始めた。
あばら骨、腕の骨、足の骨と、まるで木の枝でも折るかの様にバキバキと斧で叩き潰し、小さな破片にしていく。
そして小さくなったその骨のかけらをポイポイとハゲワシ達の方に向かって投げていく。
するとハゲワシ達はその骨すらもバクバクと飲み込んでいくのである。
そして男は最後に髑髏を持ってきて、
「バキッ!!」
と一振りで叩き潰し、見事にグシャグシャになったそれもハゲワシに食べさせた。
汗びっしょりになったその男はフゥと溜め息をつき、汗を拭い、淡々とした表情で丘を下りていった。
あとには何も残っていなかった。
確かに今、
僕の眼の前で、一人の人間が還るべき所へ還り、そして完全に自然の一部となったのだ。
ただそれだけのことで、後にも先にも何もない。
チベット人達はそのことを当たり前の様に理解し、そして自分たちもいつかこの天へと還っていくのだということを知っているのだろう。
僕は彼らのあのあっけらかんとした表情からそう思わずにはいられなかった。
そして僕はこの体験をきっと忘れない様にしようと思いながら、丘を下りた。
I was in the middle of the prairie.
Endless hills almost looked like sand dunes, there was a scenery I had never seen before. Was it because of the lack of oxygen or the altitude, the sky was as blue as it could possibly be.
In the deep blue sky, countless vultures flew in circles with their vast wings wide open. It could be over a hundred of them. They made spontaneous descents making sharp noises as they gracefully made circles. Some of them
descended almost to graze my head. I continued my way hoping that they won’t take my head away.
I was in Tibet to witness sky burial. A burial ceremony which let the predatory birds eat a human corpse, it is a way to realize impermanence of life, a common ritual in Tibet.
Every town has their own ceremonial rock table for the sky burial. Bodies of deceased are dissolved into the nature as if it is supposed to be. It is believed a soul which left a body will reincarnate into a new life, the endless circle of birth.
A soul is considered as life in Tibet, therefore a body of a deceased without a soul is only an empty vessel. Offering own empty vessel to fuel the other lives may be a way to return the favor for the lives taken for the survival of the person. Sky burial is deeply connected to the Buddhist belief.
I made it to the burial table. It was not expected exactly which date sky burial was to be held but the relatives were already gathered and preparing for the ceremony at the table on the day I arrived.
It was an empty space only with a square shaped flat rock. As I stood still and observed birds from the hill top, I saw many men carrying a plastic bag coming closer to the hill. The men took out ‘the thing’ out of the bag and unwrapped the yellow cloth. The body of the deceased without the soul, an empty vessel was exposed in front of our eyes with a distinct smell.
!
It looked like floating in the air, his powerless arms and legs hanging down, under the deep blue sky. The body was surrounded by the many men.
I had a strange feeling. Indeed the body no longer had the soul however the part of me never could believe what I observed. I felt my mind disconnecting from the reality in front of me. At the same time, my understanding of the death was being shaken and challenged. I kept staring at the preparation but my thoughts were floating like the soul of the deceased.
It was a male body.
I had no idea about how many days had passed after his departure. The color of the skin was turned brown, the arms and the legs were twisted unnaturally. It was easy to judge even from the distance the stiffness and low temperature of the body.
The vultures kept calm until the smell of the body started to attract their attention. However the wall of men surrounding the body kept the vultures away and they waited for the moment to come.
All the men stood still just staring at the deceased except for one man. The man had a knife in hand, dressed in a blue plastic bag, and cut the body into pieces.
The body was laid facing down, the back, the arms, the legs, the head were all cut off, and inner body under the skin was all exposed.
This procedure was not to violate the deceased but it was to help the vultures to eat them easily. The body was completely disassembled in about 10 minutes.
The moment, the man with the knife stood up and the surrounding men left the deceased, all the vultures kept waiting till then screeched and jumped into the body.
Countless vultures blocked the view of the body in an instant. Vultures’ head turned red with blood as they picked the meat with their sharp beak. Some of them battled hard, the offensive and defensive battles to make sure to save their own share. Once in a while, a piece of meat was thrown into the air and left from the battle field, then again several vultures jumped in and created a new battle field over the piece of meat. It was intense.
I trembled witnessing the harsh reality of the nature and honoring the Tibetan belief of life and death. Mixed emotions rushed through my body and all my senses were awoken to sense what was there. The vultures continued the battle for their survival while I was lost in the thought.
After a while, the man who was with the knife earlier now holding a stick, started to chase away the vultures. After the vultures left, bones were the only thing remained. It was the inevitable evidence of the fact that all was there went inside of the stomach of the vultures.
The knife man approached the bones, having an axe in hand instead and started to crush the bones. The rib, the arms, the legs, they were all crushed and were made into small fragmented pieces. Then the man threw those fragmented bone pieces towards the vultures. The vultures swallowed them without a hesitation.
Finally, the man took the skull and smashed in a swing and let the vultures eat the smashed skull.
The man was all sweat and took a deep breath, wiped his sweat and calmly made his way down the hill.
There was nothing left after all.
What I witnessed was, one man going back to the place where he was supposed to be, dissolving into the nature. That was all. Maybe Tibetans naturally know they will be dissolving into the nature when the time comes. I could not help but think it was nothing unusual for the Tibetans, judging from their facial expressions.
I told myself I shall never forget what I witnessed as I went down the hill.